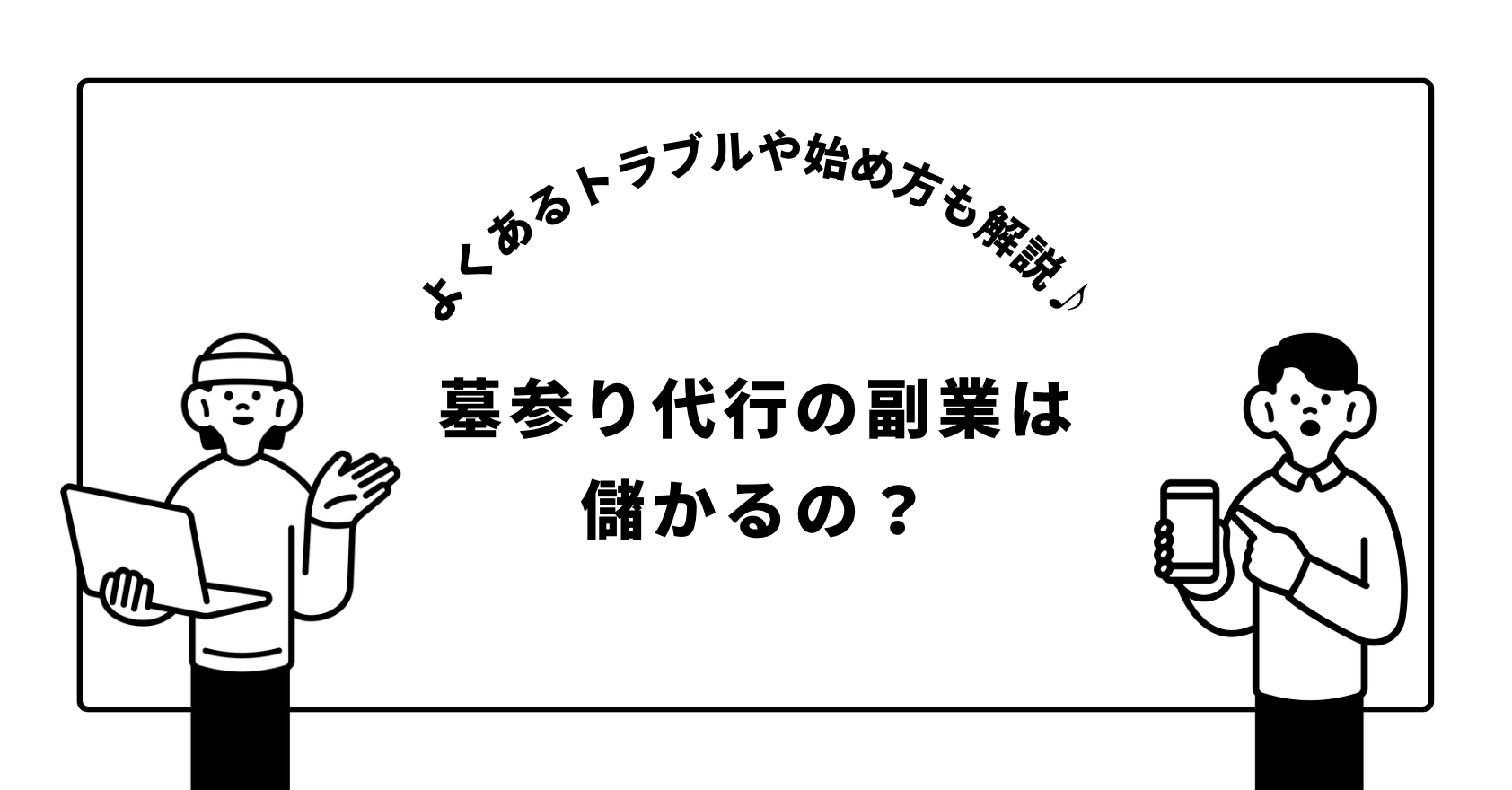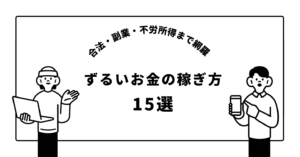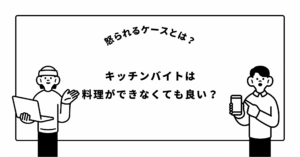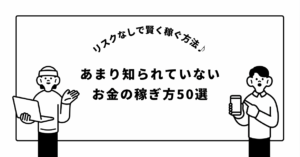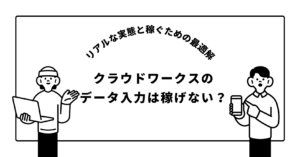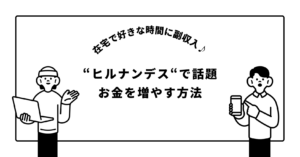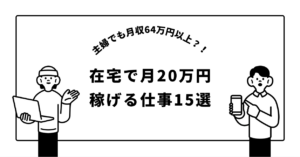近年、「墓参り代行」という仕事が注目を集めています。
高齢化や都市部への人口集中により、お墓参りに行きたくても行けない人が増えています。
そんな人々の代わりに、お墓を掃除し、供養を行うのが「墓参り代行」の仕事です。
「副業として稼げるの?」「始めるにはどうすればいい?」「トラブルはないの?」
そんな疑問を持っている方のために、この記事では、墓参り代行の仕事内容・収益性・始め方・注意点について詳しく解説します。
副業として墓参り代行を考えている方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
墓参り代行とは

墓参り代行とは、お墓参りに行けない人に代わってお墓の清掃や供養を行うサービスです。
依頼者の多くは、遠方に住んでいるため頻繁にお墓参りができない人や、高齢・病気で移動が難しい人などです。
墓参り代行の主な業務には、以下のような作業があります。
- 墓石や周辺の清掃(ブラシやスポンジで汚れを落とす)
- 献花やお供え物の設置
- 線香をあげて合掌・供養
- 事前の現地調査(お墓の状態確認と写真撮影)
お墓参りは日本の伝統文化の一つであり、多くの人にとって大切な儀式です。
しかし、生活スタイルの変化により、これまでのように家族そろってお墓参りをするのが難しくなってきました。
そのため、墓参り代行サービスは、単なる清掃だけでなく、依頼者の「想い」を届ける役割も果たしています。
墓参り代行の需要が拡大している理由
近年、墓参り代行サービスの需要は急速に拡大しています。
その背景には、以下のような要因があります。
- 高齢化の進行 – お墓を管理する世代が高齢化し、移動が困難になっている
- 遠方居住者の増加 – 都市部への人口集中により、実家のお墓が遠くなり足を運ぶのが難しい
- 共働き家庭の増加 – 忙しい生活の中で、お墓参りに行く時間を確保できない
- 寺院・霊園のサービス拡充 – 一部の寺院や霊園が公式に代行サービスを提供し始めている
特に、都市部に住む人々の間では「お盆やお彼岸の時期に帰省できない」という悩みを持つ人が多く、墓参り代行を利用するケースが増加しています。
また、インターネットの普及により、ココナラなどの仲介サービスを通じて個人が墓参り代行を提供するケースも増加しています。

こうした背景から、墓参り代行は今後も成長が期待される副業の一つです。
市場規模と今後の成長予測
墓参り代行市場はまだ新しい分野ですが、今後さらに拡大が見込まれています。現在の市場規模は正確な統計がないものの、業者や個人が提供するサービスが増えていることから、需要の拡大は明らかです。
以下の要因が、今後の市場成長を後押しすると考えられます。
- ふるさと納税の返礼品としての採用 – 一部の自治体では、墓参り代行を返礼品として提供
- オンラインでの依頼が可能に – 依頼者が簡単にサービスを探しやすくなった
- 少子化・単身世帯の増加 – 家族全員が遠方に住むケースが増え、お墓の管理が困難に
また、既存の清掃業やハウスクリーニング業者が墓参り代行サービスを取り入れる動きもあり、今後さらに業界全体が成長していくと予想されます。
特に、お盆やお彼岸などの繁忙期には需要が急増するため、計画的に働けば副業として十分な収益を得ることが可能です。
墓参り代行の仕事内容

お墓の清掃作業
墓参り代行の中心となる業務が「お墓の清掃」です。長期間放置されたお墓には、苔やカビが生えたり、落ち葉やゴミが溜まったりすることがあります。
そのため、清掃作業は依頼者にとって重要なポイントとなります。
主な清掃内容は以下の通りです。
- 墓石の洗浄:専用のブラシやスポンジを使用し、墓石の汚れを落とす
- 彫刻部分のクリーニング:文字部分に溜まったほこりやコケを丁寧に除去
- 墓地周辺の掃除:落ち葉やゴミの回収、雑草の除去
- 供物台・花立ての洗浄:花瓶や線香立ての汚れを落とす
基本的には手作業での清掃が中心ですが、汚れがひどい場合には専用の洗剤や高圧洗浄機を使うこともあります。
ただし、強い洗剤は墓石を傷める可能性があるため、使用には注意が必要です。
献花・線香供養の代行
清掃作業の後には、お墓参りの一環として「献花・線香供養」の代行も行います。
これは、依頼者の希望に応じて実施されることが多く、「ただ掃除をするだけでなく、しっかりと供養してほしい」というニーズに応える形です。
献花や線香供養の具体的な流れは以下の通りです。
- 献花:依頼者の希望に沿った花(菊・ユリなど)をお供え
- お供え物:果物や故人の好物などを設置(事前に依頼者と相談)
- 線香の点火:適切な本数の線香を焚き、故人の冥福を祈る
- 合掌・礼拝:依頼者の代わりに手を合わせ、祈る
また、墓参り代行を利用する人の中には「直接お墓に行けないが、気持ちだけでも届けたい」という人も多いです。
そのため、サービスの質を高めるためにも、供養の姿勢をしっかりと持って取り組むことが重要です。
事前調査と依頼主への報告
長年放置されていたお墓の場合、事前に現地調査を行い、現在の状態を依頼者に報告することがあります。
特に、遠方に住んでいる依頼者にとっては、お墓の状況を知る手段がないため、事前調査は重要なサービスの一つです。
事前調査の流れは以下の通りです。
- お墓の現状を確認:墓石の汚れ具合、倒壊の有無、雑草の状態などをチェック
- 写真撮影:清掃前の状態を撮影し、依頼者にメールやLINEで送付
- 清掃プランの提案:どの程度の作業が必要かを説明し、追加サービスの有無を確認
この事前調査を行うことで、依頼者は作業内容を具体的に把握でき、安心して依頼できるようになります。
さらに、清掃後にも「作業前後の比較写真」を送ることで、信頼度を高めることができます。
依頼されるタイミングと繁忙期
墓参り代行の依頼が多くなるのは、日本の伝統的な供養の時期と密接に関係しています。
特に繁忙期となるのは以下のような時期です。
| 時期 | 主な行事 | 依頼が増える理由 |
|---|---|---|
| 3月・9月 | 春・秋のお彼岸 | 先祖供養のために多くの人が墓参りをする時期 |
| 7月〜8月 | お盆 | ご先祖様を迎えるために墓参りをする人が増える |
| 12月〜1月 | 年末年始 | 新年を迎える前にお墓をきれいにしたいという需要が高まる |
| 故人の命日 | 個別の法要 | 特定の家族が墓参りをしたいと考えるタイミング |
特に、お盆やお彼岸の時期は、業者にとってのピークシーズンとなり、依頼が集中するため、スケジュール管理が重要です。
逆に、閑散期となる冬場(1月〜2月)は依頼が少なくなるため、他の仕事と並行して取り組むことを考えるのも一つの戦略です。
墓参り代行を副業にする方法
墓参り代行業者のアルバイトとして働く
墓参り代行を副業として始める最も手軽な方法が、既存の墓参り代行業者のアルバイトとして働くことです。
墓石販売店や清掃業者、家事代行業者などが墓参り代行サービスを提供しているケースが多く、求人情報サイトや業者の公式サイトで募集されることがあります。
墓参り代行業者のアルバイトの特徴:
- 安定した仕事が得られる(依頼が安定しているため、集客の必要がない)
- 初心者でも始めやすい(マニュアルや研修がある場合が多い)
- 時給制や固定報酬(1回の作業で5,000円〜10,000円程度)
一方で、時給換算すると1,000円〜1,500円程度のケースも多く、個人で受注するよりも収益性は低くなります。
副業として気軽に始めたい人や、最初に経験を積みたい人に向いている方法です。
個人で墓参り代行サービスを起業する
より高収入を目指したい場合は、個人で墓参り代行サービスを立ち上げるのも一つの方法です。
自分で価格設定ができるため、1回の依頼で1万円以上稼ぐことも可能になります。
個人で墓参り代行を始める流れ:
- 事業の形態を決める(副業として個人事業主で始めるのが一般的)
- サービス内容と料金を決定(基本清掃・供養・写真報告などを含める)
- 集客手段を用意(SNS・ブログ・チラシ・知人からの紹介など)
- 必要な道具を準備(掃除用具、カメラ、手袋、エプロンなど)
- 営業を開始(実績を積み、口コミを増やす)
ただし、個人で営業する場合、最初は依頼を獲得するまでの集客が難しい点に注意が必要です。
地元の人に向けたチラシ配布や、Googleマップへの登録など、認知度を上げる工夫が求められます。
仲介サービスを活用して副業を始める
「いきなり個人で始めるのは不安…」という場合は、仲介サービスを利用して仕事を受注する方法もあります。
代表的なプラットフォームには以下のようなものがあります。
- ココナラ(スキルマーケットで墓参り代行を出品)
- くらしのマーケット(清掃・家事代行サービスの一環として登録可能)
- タイムチケット(時間単位でサービスを販売)
仲介サービスを活用するメリット:
- 既にプラットフォームの集客力があるため、依頼を獲得しやすい
- 自分で価格を設定できる(相場5,000円〜15,000円)
- 実績を積めば、リピーターを増やしやすい
ただし、プラットフォームごとに手数料(10〜20%程度)がかかる点には注意が必要です。
必要な道具・初期費用の目安
墓参り代行を始めるにあたっては、最低限の道具を揃える必要があります。
個人で起業する場合の初期費用の目安は以下の通りです。
| 道具・設備 | 費用の目安 |
|---|---|
| 掃除用具(ブラシ、スポンジ、洗剤) | 5,000円〜10,000円 |
| 手袋・エプロン | 1,000円〜3,000円 |
| カメラ(スマホ可) | 0円(スマホ利用の場合) |
| 交通費 | 依頼ごとに変動 |
| 名刺・チラシ | 3,000円〜5,000円 |
| Webサイト制作(必要に応じて) | 10,000円〜50,000円 |
最低限の道具を揃えるだけなら、1万円〜2万円程度でスタート可能です。
より本格的に営業する場合は、広告費やWebサイト制作費も考慮する必要があります。
墓参り代行に資格は必要?
墓参り代行を始めるにあたって、特別な資格は必要ありません。
しかし、依頼者の大切なご先祖様を扱う仕事であるため、最低限の知識やマナーを身につけることが重要です。
役立つ知識・スキル:
- お墓の正しい掃除方法(墓石を傷つけない洗浄方法を学ぶ)
- 供養マナー(合掌の仕方、線香の本数など)
- 写真撮影スキル(ビフォーアフターを分かりやすく伝える)
また、「遺品整理士」や「終活アドバイザー」などの資格を取得しておくと、依頼者からの信頼が高まり、仕事の幅を広げることができるでしょう。
墓参り代行の副業をするメリット・デメリット

メリット① 高単価で短時間の仕事が多い
墓参り代行は、比較的短時間の作業で高単価が見込める副業の一つです。
一般的な作業時間は1〜2時間ほどですが、1回の報酬は5,000円〜15,000円程度が相場とされています。
他の副業と比較すると、次のような収益性の違いがあります。
| 副業の種類 | 平均時給 |
|---|---|
| 墓参り代行 | 2,500円〜7,500円 |
| コンビニ・飲食店バイト | 1,000円〜1,300円 |
| データ入力・アンケートモニター | 500円〜1,000円 |
作業内容がシンプルなため、特別なスキルが不要なのも魅力の一つです。
副業として効率よく稼ぎたい人には、特におすすめの仕事と言えます。
メリット② 需要が増加しており将来性がある
墓参り代行の需要は年々増加しており、今後も拡大が見込まれています。
その背景には、以下のような社会的要因があります。
- 高齢化の進行:お墓参りが困難な高齢者が増加
- 都市部への人口集中:地方にお墓があるが、遠方で訪問できない人が増加
- 共働き・多忙なライフスタイル:仕事や家庭の都合で時間が取れない
また、ふるさと納税の返礼品として墓参り代行を提供する自治体も増えており、サービスとしての認知度が高まっています。
今後も需要の増加が見込まれるため、長期的に副業として成り立つ可能性が高いです。
メリット③ 自分のペースで働ける
墓参り代行の副業は、依頼を受けるペースを自分で調整できる点が大きなメリットです。
特に、個人で受注する場合は、働く時間や案件の数を自由に決められます。
例えば、以下のような働き方が可能です。
- 週末だけ副業として受注
- 繁忙期(お盆・お彼岸)に集中して稼ぐ
- 平日の空いた時間に効率よく作業する
また、オンラインの仲介サービス(ココナラ・くらしのマーケットなど)を活用すれば、隙間時間に受注管理ができるため、本業との両立もしやすいです。
デメリット① 体力的に負担が大きい
墓参り代行の仕事は、思った以上に体力を使います。
特に、お墓の清掃では次のような作業が必要になります。
- 墓石の洗浄(しゃがみながらの作業が多い)
- 雑草の除去(力仕事になることも)
- 墓地内の移動(広い霊園では長距離を歩くこともある)
夏場の炎天下での作業は特に過酷で、熱中症対策が必要です。
また、腰や膝に負担がかかるため、長時間の作業が苦手な人には向かない場合もあります。
デメリット② 季節によって依頼数が変動する
墓参り代行は、年間を通じて安定して依頼が入る仕事ではありません。
特に、お盆(7〜8月)やお彼岸(3月・9月)などの時期には依頼が急増するものの、閑散期(1〜2月、5〜6月)には仕事が激減することもあります。
以下の表は、一般的な墓参り代行の依頼が増える時期です。
| 時期 | 依頼の多さ |
|---|---|
| 3月(春のお彼岸) | 多い |
| 7月〜8月(お盆) | 非常に多い |
| 9月(秋のお彼岸) | 多い |
| 12月〜1月(年末年始) | 中程度 |
| 1〜2月、5〜6月 | 少ない |
閑散期の対策として、清掃代行や家事代行と組み合わせたサービスを提供するのも一つの手です。
デメリット③ 依頼者とのトラブルリスクがある
墓参り代行は依頼者の大切な家族の供養に関わる仕事であるため、些細なミスがトラブルにつながる可能性があります。
主なトラブル事例として、以下のようなものがあります。
- 掃除の仕上がりに対するクレーム(墓石の汚れが残っているなど)
- お供え物の間違い(依頼者の意図と異なる献花を用意してしまう)
- 墓石を傷つけてしまう(強い洗剤や金属ブラシの使用による損傷)
これらのトラブルを防ぐためには、事前のヒアリングをしっかり行い、作業前後の写真を撮影して依頼者に報告することが重要です。
また、万が一のトラブルに備えて、賠償責任保険に加入することも検討すると安心です。
墓参り代行でよくあるトラブルと対策

お墓を傷つけてしまった場合
墓参り代行で最も注意しなければならないのが「お墓を傷つけてしまう」トラブルです。
墓石は素材によっては非常にデリケートで、誤った清掃方法を行うと、表面に傷がついたり変色したりする可能性があります。
墓石を傷つける主な原因:
- 金属製のブラシやタワシを使用してしまう
- 酸性の洗剤を使い、墓石の色が変わる
- 強く擦りすぎて石の表面を削ってしまう
トラブルを防ぐ対策:
- 柔らかいスポンジや布を使用する
- 中性洗剤を使い、石材に優しい方法で清掃する
- 水拭きを徹底し、洗剤が墓石に残らないようにする
- 清掃前後の写真を撮り、作業内容を記録する
万が一墓石に傷をつけてしまった場合は、すぐに依頼者に報告し、状況を説明することが重要です。
また、賠償責任保険に加入しておけば、万が一のトラブル時にも金銭的なリスクを軽減できます。
依頼者との認識違いによるトラブル
依頼者とのコミュニケーション不足によるトラブルも、墓参り代行ではよく発生します。
特に、清掃範囲や供養の方法について依頼者が具体的な指示を出していなかった場合、作業後に「イメージと違う」といったクレームにつながることがあります。
よくある認識違いの例:
- 掃除の仕上がりが依頼者の期待に届かなかった
- 希望していた花と異なるものを供えた
- 作業完了報告の写真が不足していた
- 依頼者の親族が知らず、勝手に掃除をされたと誤解された
トラブルを防ぐ対策:
- 依頼前に清掃内容・供養方法を細かく確認する
- 清掃範囲・供花の種類などを事前に写真で共有する
- 作業前後の写真を撮影し、詳細な報告を行う
- 供養方法に関する依頼者の宗派・信仰に配慮する
特に、リピーターを増やすためには、細かい配慮と事前のすり合わせが重要です。
少しでも不安があれば、依頼者に確認を取りながら作業を進めると、信頼関係の構築につながります。
法律やマナーに関する注意点
墓参り代行は、単なる清掃代行ではなく、ご先祖様を供養する行為でもあります。
そのため、法律やマナーを守らないと、依頼者や墓地管理者とのトラブルに発展する可能性があります。
法律やマナー違反の例:
- 許可を取らずに霊園や墓地に立ち入る
- 他人の墓地の敷地に入る、ゴミを放置する
- 宗派・家族の意向を無視した供養を行う
- 他人の目がある中で撮影をし、プライバシーを侵害する
トラブルを防ぐ対策:
- 霊園・墓地の管理者に事前に許可を取る
- 他の墓の敷地に立ち入らないよう注意する
- 宗派・家族の希望を必ず確認し、意向に沿った供養を行う
- 写真撮影は依頼者の同意を得てから行う
また、近年では墓参り代行に否定的な意見を持つ人もいるため、依頼者の親族が知らない場合にトラブルになることがあります。
依頼者としっかりとコミュニケーションを取り、全員が納得した上でサービスを提供することが重要です。
墓参り代行の副業を成功させるためのポイント
信頼を得るためのサービスのコツ
墓参り代行の仕事では、依頼者との信頼関係が何よりも重要です。
特に、お墓参りは故人を偲ぶ大切な行為であるため、「丁寧な仕事」「誠実な対応」が求められます。
信頼を得るためのポイント:
- 作業前後の写真を必ず送る:清掃前後の状態を撮影し、ビフォーアフターを明確に伝える
- 依頼内容を細かく確認:献花の種類や供物の有無など、依頼者の希望を正確に把握する
- 定期的な報告:リピーター向けに「次回の清掃時期の提案」を行い、信頼関係を築く
- 丁寧な対応を徹底:お墓の扱い方や供養の作法を学び、依頼者に安心感を与える
墓参り代行は、「依頼者の代わりにただ掃除をする仕事」ではなく、「故人や家族への想いを大切にする仕事」です。
その意識を持つことが、信頼を得るための最大のポイントとなります。
口コミ・リピーターを増やす方法
副業として墓参り代行を続ける場合、リピーターを増やすことが安定収入につながります。
特に、お盆やお彼岸などの繁忙期に合わせて定期依頼を獲得できると、効率的に収益を上げることができます。
口コミ・リピーターを増やすための施策:
- 作業完了後に次回の提案をする:「次のお彼岸や命日に合わせて、清掃を予約しませんか?」と提案
- 依頼者からのフィードバックを大切にする:サービス後に感想を聞き、改善につなげる
- 口コミ投稿を促す:満足した依頼者にレビューを書いてもらう(ココナラやくらしのマーケットなど)
- お得なリピートプランを用意:「年間契約割引」「次回予約割引」などの特典を設定
また、地域の霊園や寺院と提携し、定期的な清掃サービスを提供することで、安定した依頼を得ることも可能です。
差別化できるオプションサービスの提供
競争が激化する中で、他の代行業者と差別化するためには、基本サービスに加えてオプションを提供するのも有効です。
おすすめのオプションサービス:
- 墓石コーティング:汚れを防ぐ特殊コーティングを施し、次回の清掃を楽にする
- 動画報告サービス:作業中やお参りの様子を動画で撮影し、依頼者に送信
- 生花の定期交換:一定期間ごとにお花を交換するプランを提供
- 法要の手配サポート:僧侶の読経を手配するオプション
こうした付加価値のあるサービスを提供することで、他の業者と差別化し、高単価な案件を獲得しやすくなります。
墓参り代行の副業まとめ
墓参り代行は、今後も需要が拡大する可能性の高い副業です。
短時間で高収入が見込める一方、体力的な負担や依頼者との信頼関係が重要な仕事でもあります。
墓参り代行の副業を成功させるためのポイント
- お墓を傷つけないよう、適切な清掃方法を学ぶ
- 作業前後の写真を送るなど、依頼者に安心感を与える
- 口コミやリピーターを増やし、安定した収入源を確保する
- 差別化できるオプションを提供し、高単価案件を獲得する
個人で始める場合は、仲介サービスを活用しながら実績を積み、徐々に独自の集客方法を確立していくのが成功の鍵です。
墓参り代行は、地域密着型のビジネスとしても成り立つため、「お墓をきれいにするだけでなく、供養の気持ちを大切にする」ことを意識しながら取り組んでいきましょう。